こんにちは、Hassyです。
現在、僕は簿記にチャレンジ中です!
簿記初級から始め簿記3級の取得を目指してます。
| 試験日: | 2021年2月28日 |
| 試験科目: | 簿記3級 |
| 学習期間: | 約3ヶ月 |
簿記の試験などについては〝簿記-商工会議所の検定試験〟へ
『ふくしままさゆきさんのホントにシリーズ』
4時間で習得!ホントにゼロからの簿記初級 テキスト&問題集(Kindle本)
ホントにゼロからの簿記3級(Kindle本)
『ふくしままさゆきさんのYouTube』
\ふくしまさんのKindleが無料に!/
※30日以内に解約すれば料金は一切掛かりません
この記事は
簿記3級の内容で、決算整理仕訳(2/3)ついて理解していきます。今回のテーマは、
決算整理事項
収益・費用の前払い・前受けと未収・未払いの計上
固定資産の減価償却
貸倒引当金の設定
参考教科書をもとに簿記3級の個別のテーマを理解していきます。今回は3回に渡ってお届けする【決算整理仕訳】の第2部についてまとめていきます。
ではまず、「収益・費用の前払い・前受けと未収・未払いの計上」から理解していきます。
簿記3級の決算整理事項④~⑥/⑩


簿記3級の決算整理事項
現金過不足の処理
当座預金のマイナス残高の負債振替
費用処理した項目の貯蔵品への振替
収益・費用の前払い・前受けと未収・未払いの計上
固定資産の減価償却
貸倒引当金の設定
商品売上原価の算定(三分法の決算整理仕訳)
消費税の処理
法人税等の処理
利益の会計処理
今回は決算整理事項の④~⑥について理解していきます。
④:収益・費用の前払い・前受けと未収・未払いの経常
前払費用(資産)
すでに代金を支払ったけど、その恩恵(用役-ようえき)をまだ受けていない
全額を費用計上しているので、決算時点での未経過分を前払い勘定に振り替える(当期に計上した費用の一部は当期に負担する費用ではない為、減少させる)
前払い分は将来その用役を受けることができる権利
借方は前払勘定、貸方は費用勘定
前受収益(負債)
すでに代金を受け取ったけど、その恩恵(用役-ようえき)をまだ与えていない
全額を収益計上しているので、決算時点での未経過分を前受勘定に振り替える(当期に計上した収益の一部は当期に負担する収益ではない為、減少させる)
前払い分は将来その用役を受けることができる権利
借方は収益勘定、貸方は前受収益勘定
未払費用(負債)
すでに用役(恩恵)を受けたけど、その代金をまだ払っていない
まだお金を払っていないので期中の仕訳はなし、決算時点での経過分を未払勘定として計上
借方は費用勘定、貸方は未払勘定
未収収益(資産)
すでに用役(恩恵)を与えたけど、まだ代金を受け取っていない
まだお金を受け取っていないので期中の仕訳はなし、決算時点での経過分を未収勘定として計上
借方は未収勘定、貸方は収益勘定
※これら4種類の仕訳は翌期に再振振替仕訳(逆仕訳)をする
では、具体的な例題で理解していきます。
『借主Aは貸主Bから事務所用オフィスを賃貸している。家賃(1ヶ月10万円)は毎月、前月末までに支払うことになっているため、借主Aは毎月20日に現金で支払っている』
まずは、頭を整理しやすくする為に、期中での仕訳を考えます。
借主A
家賃10万円を前月の20日に前払い
貸主B
家賃10万円を前月の20日に前受け
期中
借主A
| (借)支払家賃100,000 | (貸)現金100,000 |
貸主B
| (借)現金100,000 | (貸)受取家賃100,000 |
上記の仕訳を毎月(4月~3月)行う
すると、3月の仕訳に関しては、翌年の賃料を計上している事となる。
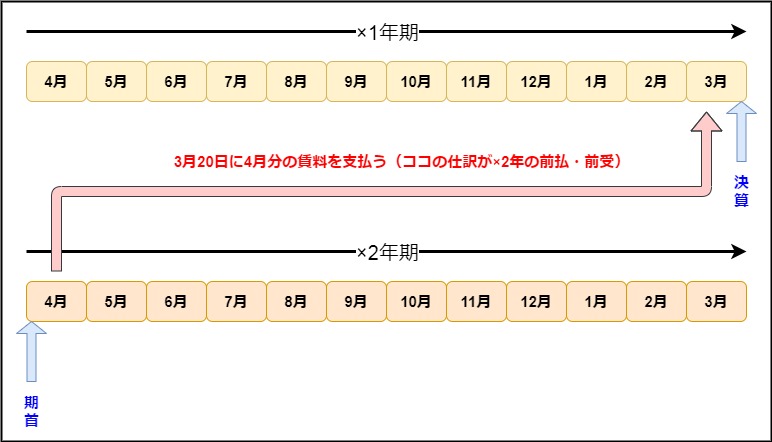
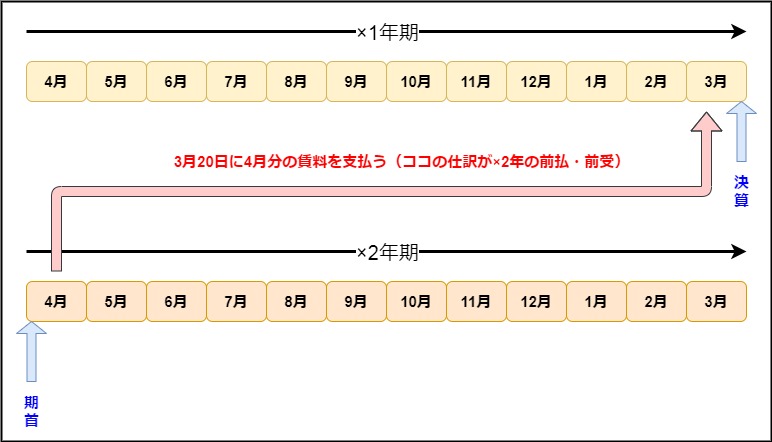
カレンダー的にイメージするとこんな感じ。
そこで、決算整理仕訳の為にポイントをまとめると
借主A
3月20日に4月分の家賃を前払いしている
代金は支払い済みなのに4月分の用役を受けていない(前払勘定)
借方は前払勘定、貸方は費用勘定(費用勘定の減少)
貸主B
3月20日に4月分の家賃を前受けしている
代金は受け取っているのに、4月分の用役を与えていない(前受勘定)
借方は収益勘定、貸方前受け勘定(収益勘定の減少)
こんな感じで、期末の仕訳は、
決算整理仕訳
借主A
| (借)前払家賃100,000 | (貸)支払家賃100,000 |
貸主B
| (借)受取家賃100,000 | (貸)前受家賃100,000 |
家賃が後払いの場合、3月分賃料について
貸主A
借方は「支払家賃」、貸方「未払家賃」
| (借)支払家賃100,000 | (貸)未払家賃100,000 |
貸主B
借方は「未収家賃」、貸方は「受取家賃」
| (借)未収家賃100,000 | (貸)受取家賃100,000 |
さらに、社会保険料の会計処理の例題を使って、理解を深めます。
『給料計算期間が2月21日~3月20日で3月28日支払いの給料総額が400万円、その給料に関する所得税の源泉徴収が30万円、社会保険料控除額が40万円』であれば、従業員には3月28日に330万円が支払われます。
会社側は「預かった70万円」と「社会保険料会社負担分45万円」の合計(115万円)を翌4月に税務署などに納めます。当座預金から支払ったとする。』
まずは、期中の給料支払いを仕訳します
3月28日給料支給
| (借)給料4,000,000 | (貸)当座預金3,300,000 |
| (貸)所得税預り金300,000 | |
| (貸)社会保険料預り金400,000 |
期中なら、この翌月に納付をすればいいけど、4月になると次の期中なってしまうので、3月中で処理をします。
つまり、
期中は、【支払い→納付】の繰り返しですが、期末(3月31日)だけは違う仕訳になるってことですね。
決算時の社会保険料
預り金(所得税・社会保険料)は負債なので、納付まで放置
法定福利費(費用)は未払い状態なので、費用計上&未払計上
翌期首に再振替仕訳を忘れずに
決算(費用の未払計上)
| (借)法定福利費450,000 | (貸)未払法定福利費450,000 |
期首(再振替仕訳)
| (借)未払法定福利費450,000 | (貸)法定福利費450,000 |
4月になったので、いつもどおり納付の仕訳をする
4月納付時
| (借)所得税預り金300,000 | (貸)当座預金1,150,000 |
| (借)社会保険料預り金400,000 | |
| (借)法定福利費450,000 |
この例題だと、3月21日~3月31日までの給料(11日分)が未払いなので、「給料」を未払計上する必要もあります
決算で未払い給料が120万円の場合
決算(費用の未払計上)
| (借)給料1,200,000 | (貸)未払給料1,200,000 |
翌期首(再振替仕訳)
| (借)未払給料1,200,000 | (貸)給料1,200,000 |
⑤:固定資産の減価償却
帳簿上の価値(簿価)を減少させる。それを決算で行う
勘定科目:「減価償却累計額」(マイナスの資産)
定額法…毎年同額を減価償却
間接法…減価償却累計額での記帳方法
先頭に固定資産名を入れる
例えば、「備品価償却累計額」「建物減価償却累計額」など
※簿記3級では、定額法と間接法が出題範囲
期の途中で購入した場合は?
月割りで減価償却を計算する
例えば、年間償却額が240万の固定資産を1月1日に購入した場合は、1月1日~3月31日までの3か月分の60万円を減価償却(1か月/20万)
翌年は1年分の240万円が減価償却
これらをふまえて具体的な例題を行います
前々期首×1年4月1日に購入したパソコン(取得価格70万円、耐用年数5年、5年経過後の残存価格10万円、定額法、間接法)を本日×3年4月1日に50万円で売却した(売却代金は×3年5月末日に受け取ることとした)
年間償却額は、(70万ー10万)÷5年=12万円/年
売却時点の「備品減価償却累計額」は24万円(2年間使用)
50万円で売却
分記法
固定資産売却益
| (借)備品減価償却累計額240,000 | (貸)備品700,000 |
| (借)未収入金500,000 | (貸)固定資産売却益40,000 |
売却は、会社から資産(取得価額分)も簿価(減価償却累計額)も逆仕訳でなくします
では、「固定資産売却損」を理解する為に、同じ例題で売却額が40万円だとします。
前々期首×1年4月1日に購入したパソコン(取得価格70万円、耐用年数5年、5年経過後の残存価格10万円、定額法、間接法)を本日×3年4月1日に40万円で売却した(売却代金は×3年5月末日に受け取ることとした)
固定資産売却損
| (借)備品減価償却累計額240,000 | (貸)備品700,000 |
| (借)未収入金400,000 | |
| (借)固定資産売却損60,000 |
さらに、もう一つ「期中の途中に売却した」場合の仕訳
『前々期首×1年4月1日に購入したパソコン(取得価格70万円、耐用年数5年、5年経過後の残存価格10万円、定額法、間接法)を本日×3年4月30日に50万円で売却した(売却代金は×3年5月末日に受け取ることとした)』
年間償却額は、(70万ー10万)÷5年=12万円/年
売却時点の「備品減価償却累計額」は24万円(2年間使用)
50万円で売却
分記法
月割りの勘定科目「減価償却費」の仕訳をする
期中の途中での売却(固定資産売却益)
| (借)備品減価償却累計額240,000 | (貸)備品700,000 |
| (借)減価償却費10,000 | (貸)固定資産売却益50,000 |
| (借)未収入金500,000 |
※月割りの減価償却費(4月1日~4月30日):1ヶ月分の減価償却費(12万÷12ヶ月=1万円)
土地は減価償却をしない!
理由は、ずっと使い続けることが前提だから
⑥:貸倒引当金の設定
貸倒とは、貸したカネ・ツケ代金を回収できないこと
勘定科目
貸倒引当金(マイナスの資産)…貸倒になるものとして考えている金額
貸倒引当金繰入(費用)…回収できないと見積もった金額を費用とする。まだ貸倒が発生していなくて
※期末の仕訳を貸倒引当金の設定という
貸倒引当金の設定方法の「差額補充法」を理解します
差額補充法…設定しようとしている引当金の金額と、すでに計上している引当金との差額を計上する方法
『期末日時点での売掛金残高が10,000円あり、このうち3%が貸倒になると見積もられた。なお期末日時点で「貸倒引当金」残高は200円』
10,000円×3%=300円(設定したい貸倒引当金の金額)
設定しようとしている貸倒引当金300円ー残高200円=100円
ポイントをふまえて仕訳します
貸倒引当金繰入
| (借)貸倒引当金繰入100 | (貸)貸倒引当金100 |
※設定したい金額より残高が少ない場合は「貸倒引当金繰入」(費用)
では、設定したい金額より残高が多い場合はどうなるか理解します。
同じ例題で貸倒引当金残高が400円だとします。
『期末日時点での売掛金残高が10,000円あり、このうち3%が貸倒になると見積もられた。なお期末日時点で「貸倒引当金」残高は400円』
貸倒引当金戻入(収益)
| (貸)貸倒引当金100 | (貸)貸倒引当金戻入100 |
※設定したい金額より残高が多い場合は「貸倒引当金戻入」(収益)となる。
⑥:貸倒引当金(期中)
貸倒引当金は期末決算よりも期中が重要
貸倒引当金(期中)の論点
期中での仕訳は貸倒(貸倒は期中に起こる)
「当期のツケの売掛金」と「前期以前のツケ売掛金」は区別する
前期以前は、前期以前で決算整理仕訳している
当期の売掛金は期末日じゃないので、貸倒引当金の対象外
まずは、流れを含めたオーソドックスな例題でイメージできるようにします
- STEP1『9月1日、A店に売値100円の商品を掛けで販売』
(借)売掛金100 (貸)売上100 - STEP2『2月28日、上記売掛金のA店が倒産し、売掛金を回収できないことがわかった』
(借)貸倒損失100 (貸)売掛金100 ※貸倒損失(費用)
当期の売掛金の貸倒はとても簡単です。では、前期以前の売掛金の貸倒はどうなるかを理解します。
- STEP1『9月1日、A店に売値100円の商品を掛けで販売』
(借)売掛金100 (貸)売上100 - STEP2前期末時点で(3月31日時点)で決算整理仕訳
(借)貸倒引当金繰入 貸倒引当金 の仕訳が行われている
- STEP3『翌年度の4月30日、上記売掛金のA店が倒産し、売掛金を回収できないことがわかった』
(借)貸倒引当金100 (貸)売掛金100
当期中と前期以前の違いは、期末に決算整理仕訳で貸倒を費用処理しているので、「貸倒損失」では無く、「貸倒引当金」が借方となる
さらに理解を深めるためにもう一問
『得意先B社が倒産し、B社に対する売掛金残高10万円(全額前期中の販売によるもの)が貸し倒れた。B社倒産時点で当社の「貸倒引当金」残高は8万円』
| (借)貸倒引当金80,000 | (貸)売掛金100,000 |
| (借)貸倒損失20,000 |
では、
貸倒処理した後に回収できた場合はというと
『3月2日に、2月に掛け販売したA店が倒産し、売掛金100円が回収できないことがわかった』
| (借)貸倒損失100 | (貸)売掛金100 |
この貸倒の回収について、「当期中に回収」と「前期以前の回収」はどうなるのか?上記の例題を使って、理解します。
『3月21日になって、3月2日に貸倒処理したA店に対する売掛金のうち20円を現金で回収できた』
| (借)現金20 | (貸)貸倒損失20 |
『4月21日になって、3月2日に貸倒処理したA店に対する売掛金のうち20円を現金で回収できた』
| (借)現金20 | (貸)償却債権取立益20 |
※償却債権取立益(収益)
個別テーマ編【決算整理仕訳の第2部】は以上です。
それでは今回のまとめで終わります。
まとめ:【簿記3級】決算整理仕訳(2/3)を理解しよう!『個別テーマ編』#6


今回ご紹介した『【簿記3級】決算整理仕訳(2/3)を理解しよう!個別テーマ編#6』はいかがだったでしょうか?
『収益・費用の前払い・前受けと未収・未払いの計上』
前払費用(資産)
前受収益(負債)
未払費用(負債)
未収収益(資産)
『固定資産の減価償却』
減価償却累計額(マイナスの資産)
固定資産売却益・損
減価償却費
『貸倒引当金の設定』
貸倒引当金(マイナスの資産)
貸倒引当金繰入(費用)・戻入(収益)
貸倒損失(費用)
次回は、決算整理仕訳の第3部を理解していきます。
ではまた、Hassyでした。
を理解しよう!#6.jpg)







を理解しよう!『個別テーマ編』#5-320x180.jpg)
を理解しよう!#7-320x180.jpg)