こんにちは、Hassyです。
現在、僕は簿記にチャレンジ中です!
簿記初級から始め簿記3級の取得を目指してます。
| 試験日: | 2021年2月28日 |
| 試験科目: | 簿記3級 |
| 学習期間: | 約3ヶ月 |
簿記の試験などについては〝簿記-商工会議所の検定試験〟へ
『ふくしままさゆきさんのホントにシリーズ』
4時間で習得!ホントにゼロからの簿記初級 テキスト&問題集(Kindle本)
ホントにゼロからの簿記3級(Kindle本)
『ふくしままさゆきさんのYouTube』
\ふくしまさんのKindleが無料に!/
※30日以内に解約すれば料金は一切掛かりません
この記事は
簿記初級の内容で、それぞれ個別のテーマについて理解していきます。今回のテーマは、
現金
預金
参考教科書をもとに簿記初級の個別のテーマを理解していきます。今回は【現金・預金】ついてまとめていきます。
ではまず、「現金」から理解していきます。
現金

現金とは
手元にある現金(硬貨・紙幣)を「現金」という勘定科目を用いて仕訳する
「現金」は“資産”なので、受け取ったら(手元現金が増加するので)借方、支払ったら(手元現金が減少するので)貸方
例1:『電気代1万円を現金で支払ったら』
| (借)水道光熱費10,000 | (貸)現金10,000 |
例2『売掛金1万円を現金で回収したら』
| (借)現金10,000 | (貸)売掛金10,000 |
つまり、
【現金】は「出金」したら“貸方”、「入金」したら“借方”
簿記でいう「現金」とは硬貨・紙幣だけを指すわけではありません。その上で、「現金」での重要な論点が3つあります。
現金で3つの中心論点
通貨代用証券
現金過不足
小口現金
簿記初級では、②と③は出題範囲外なので、ここでは説明無し。
ここでは、①の通貨代用証券について理解します。
通貨代用証券
すぐにお金に換金できるものも、簿記では「現金」扱いする
他には、「配当金領収証」や「郵便為替証書」もすぐに換金できるので“現金”と同じ扱い
・『配当金領収証』…株式を保有していると送付され、指定金融機関に持参すると換金できる。
・『郵便為替証書』…郵便局に持参すると換金できる。
※これらは、【通貨代用証券】と呼び、受け取ったら勘定科目は「借方(現金)」
例:『売掛金100円の回収として、郵便為替証書を受け取ったら』
| (借)現金100 | (貸)売掛金100 |
次は、預金についてです。
預金

預金といえば
普通預金
定期預金
当座預金
普通預金と定期預金を“預金”といえば指すことが多いと思いますが、預金についての論点は小切手取引なので、当座預金についてしっかり理解していきます。
まずは、預金の仕訳例をざぁーっと仕訳していきます。
預金全般に関する仕訳
例1:『銀行へ行って現金3,000円を普通預金に預け入れた。』
| 借)普通預金3,000 | (貸)現金3,000 |
例2:『銀行へ行って現金5,000円を当座預金に預け入れた。』
| 借)当座預金5,000 | (貸)現金5,000 |
例3:『普通預金2,000円を定期預金に振り替えた。』
| 借)定期預金2,000 | (貸)普通預金2,000 |
例4『普通預金に利息1,000がついた。』
| 借)普通預金1,000 | (貸)受取利息1,000 |
例5:『手元にある3,000円の郵便為替証書。を普通預金に預け入れた。』
| 借)普通預金3,000 | (貸)現金3,000 |
ここで、注意する点は、郵便為替証書(通貨代用証券)の勘定科目を「現金」にすること。
当座預金とは?
小切手や手形を使えるようになる
銀行側の審査を受ける
利息はつかず、通帳もない
・様々な支払いに使える
・手元に現金をあまり持つ必要が無くなる(キャッシュレス化)
・当座預金には利息がつかない
つまり、当座預金口座を開くということは、小切手や手形を使いたいから開くという事ですね。
では、そんな預金の中心論点である小切手取引を次は理解していきます。
小切手取引の流れ
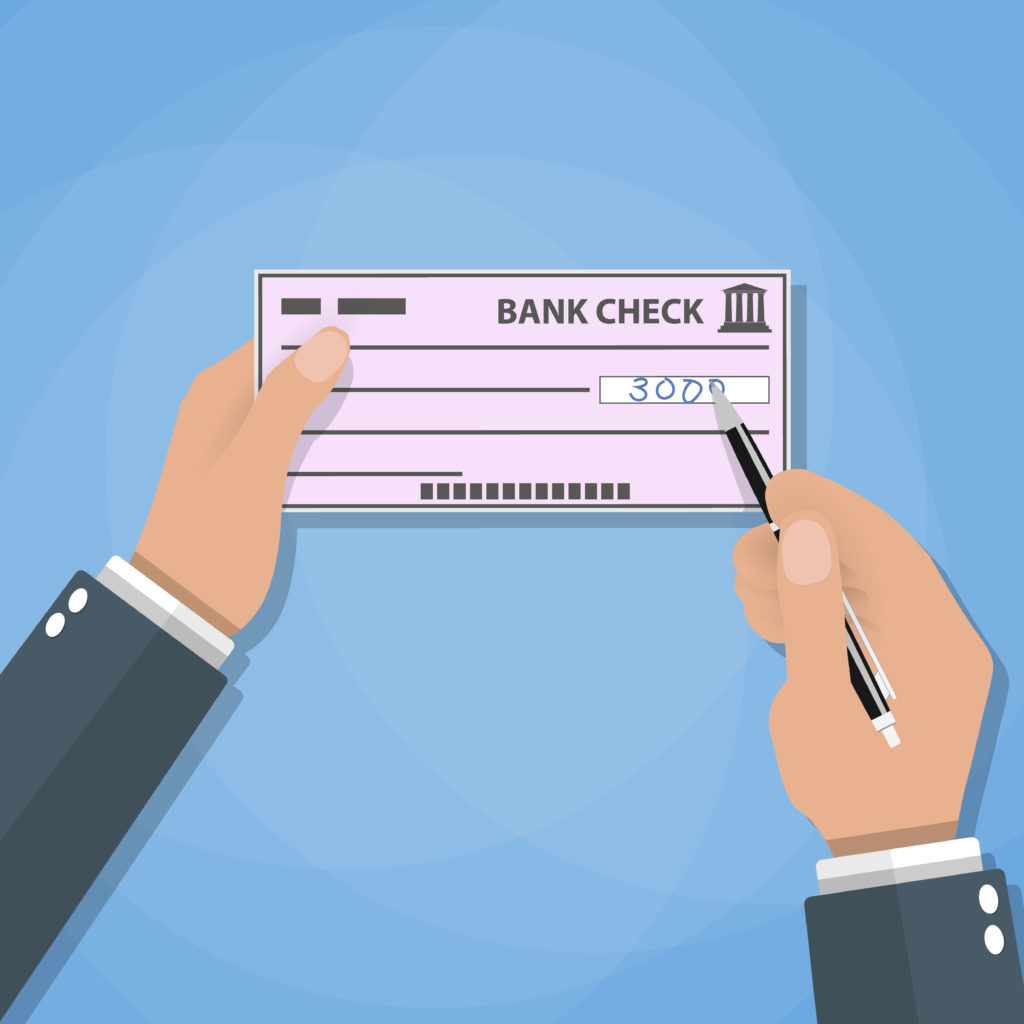
小切手の流れは大きく分けて2つあります。
小切手の流れ
自己振出の小切手の流れ
自己振出の小切手が巡り巡って戻ってくる流れ
イメージ図を以下↓に載せます。
【例1】自己振出の小切手の流れ
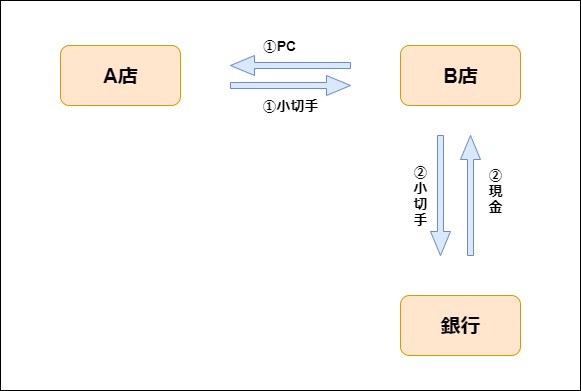
小切手を現金と同じように利用しているので、イメージしやすく仕訳も簡単ですね。
【例2】自己振出の小切手が巡り巡って戻ってくる流れ
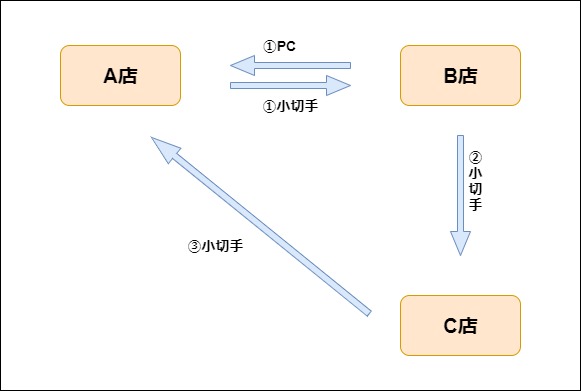
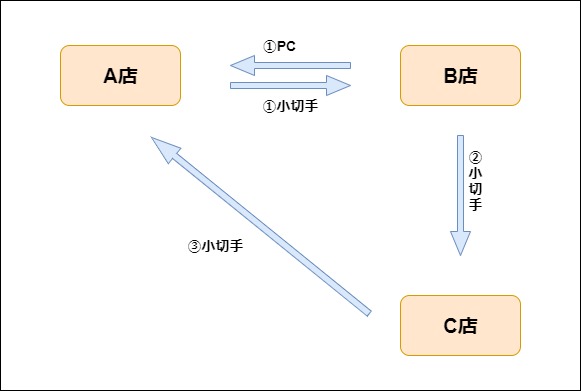
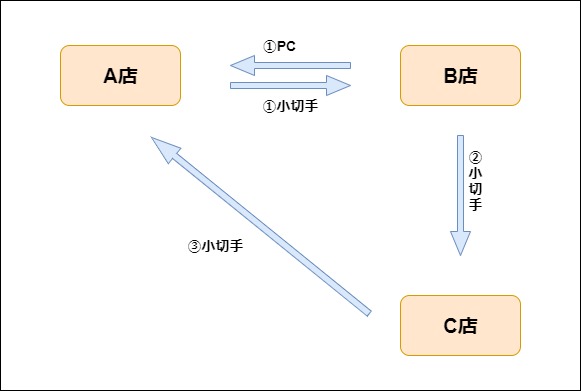
実際には、あまり無いような事例の様ですが、試験では必要な知識なので、覚えるしかありません。
小切手取引の流れはなんとなくイメージできたと思いますが、
小切手取引において、注意しなければいけないことが2つあります。
小切手の論点
仕訳の“タイミング”と“勘定科目”に注意!
自己振出の小切手が戻ってくる
これは、2つの例をやりながら、理解していきます。
まずは、『仕訳のタイミングと勘定科目』からです。
仕訳のタイミングと勘定科目
【例1】自己振出の小切手の流れ
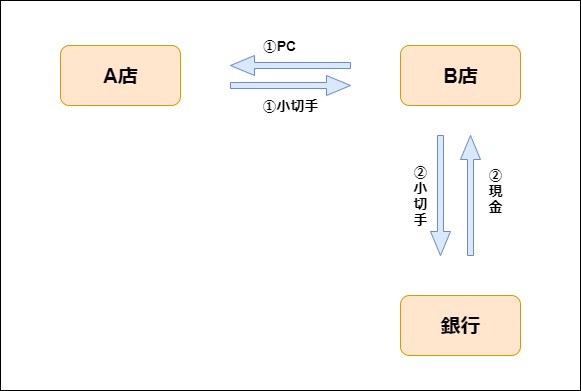
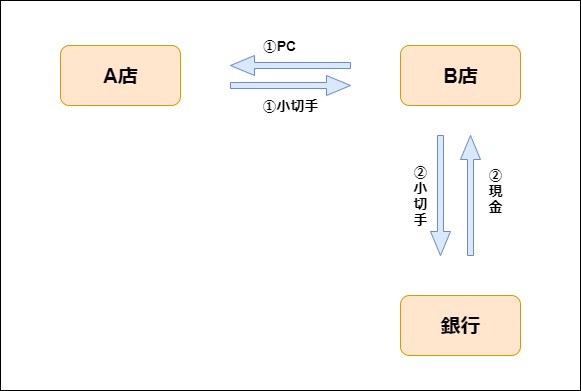
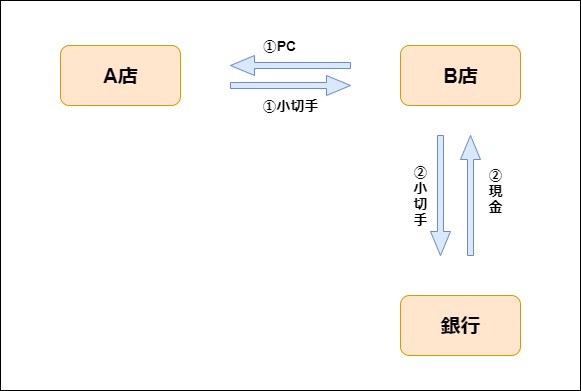
①『A店はB店(PCショップ)から、A店の事務所用のPCを20万円で購入し、小切手に金額を記入してB店に渡します(小切手を振り出すと表現する)』
②『B店はその小切手を銀行窓口へ持っていくと、窓口で現金を受け取ることができます。この現金は、A店の当座預金口座残高から引かれたものです』
上記の①と②の例題で、『仕訳のタイミングと勘定科目』を理解します。
小切手を振り出した時の仕訳のタイミングと勘定科目
・振り出した側→仕訳のタイミングは振り出した時点、勘定科目は「当座預金」
・受け取った側→仕訳のタイミングは相手から小切手を受け取った時点で、勘定科目は「現金」
このことを踏まえて上記①と②の例題を仕訳していきます。
①『A店はB店(PCショップ)から、A店の事務所用のPCを20万円で購入し、小切手に金額を記入してB店に渡します(小切手を振り出すと表現する)』
A店の仕訳
| (借)備品200,000 | (貸)当座預金200,000 |
B店の仕訳
| (借)現金200,000 | (貸)売上200,000 |
②『B店はその小切手を銀行窓口へ持っていくと、窓口で現金を受け取ることができます。この現金は、A店の当座預金口座残高から引かれたものです』
A店
仕訳無し(すでに帳簿上は当座預金が減少されているから)
B店
仕訳無し(すでに帳簿上は現金が増加しているから)
自己振出の小切手が戻ってくる
【例2】自己振出の小切手が巡り巡って戻ってくる流れ
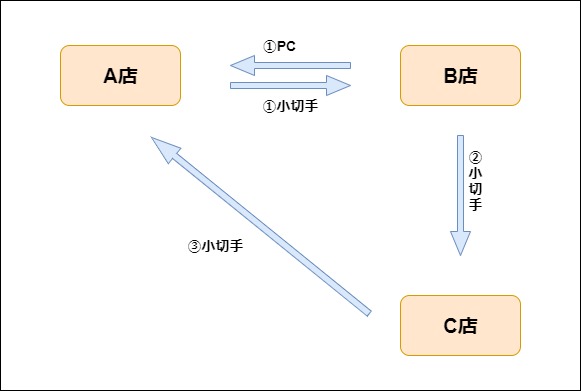
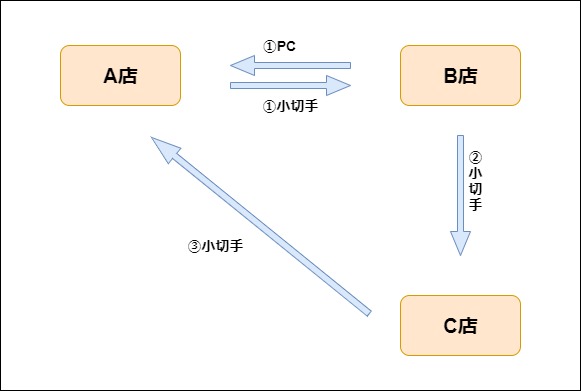
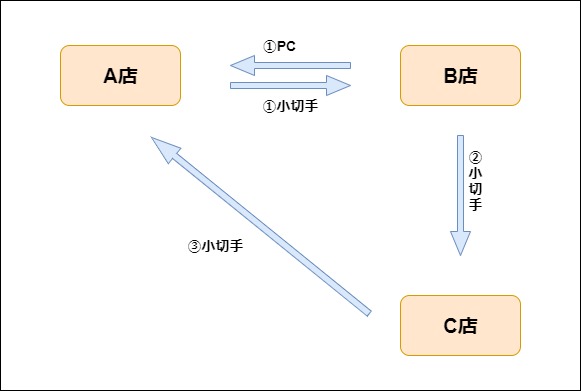
自分の振り出した小切手が巡り巡って自分に戻ってくる場合です。
「A→B→C→A」こんなイメージです。
①『A店はB店(PCショップ)から、A店の事務所用のPCを20万円で購入し、小切手に金額を記入してB店に渡します(小切手を振り出すと表現する)』
②『B店はその小切手を銀行窓口へ持っていかず、C店への商品仕入れ代金20万円の支払いのためにC店に渡した。』
③『C店は、A店からの借入金の返済のため、B店から受け取った小切手をA店に渡した。』
上記の①と②と③の例題で、『自己振出の小切手が戻ってくる』を理解します。
覚えよう!
『他人振り出しの小切手を受け取ったら現金』
『自己振出の小切手を受け取ったら当座預金』
※その小切手は誰が振り出したものなのかを注意する
この【 覚えよう!】を踏まえて上記①と②と③の例題を仕訳していきます。
①『A店はB店(PCショップ)から、A店の事務所用のPCを20万円で購入し、小切手に金額を記入してB店に渡します(小切手を振り出すと表現する)』
A店の仕訳
| (借)備品200,000 | (貸)当座預金200,000 |
B店の仕訳
| (借)現金200,000 | (貸)売上200,000 |
②『B店はその小切手を銀行窓口へ持っていかず、C店への商品仕入れ代金20万円の支払いのためにC店に渡した。』
A店の仕訳
仕訳無し(無関係)
B店の仕訳
| (借)買掛金200,000 | (貸)現金200,000 |
③『C店は、A店からの借入金の返済のため、B店から受け取った小切手をA店に渡した。』
A店の仕訳
| (借)当座預金200,000 | (貸)貸付金200,000 |
③の例題は下の↓イメージ図で赤く囲った取引です。
【例2】自己振出の小切手が巡り巡って戻ってくる流れ
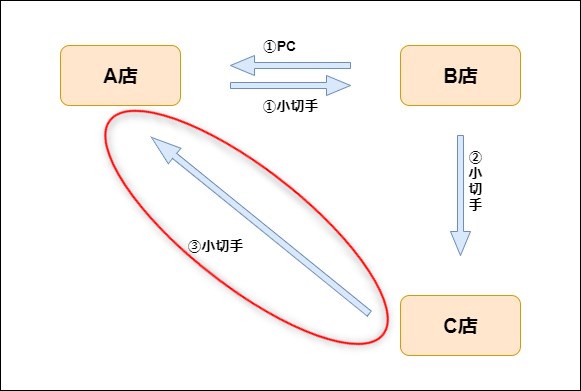
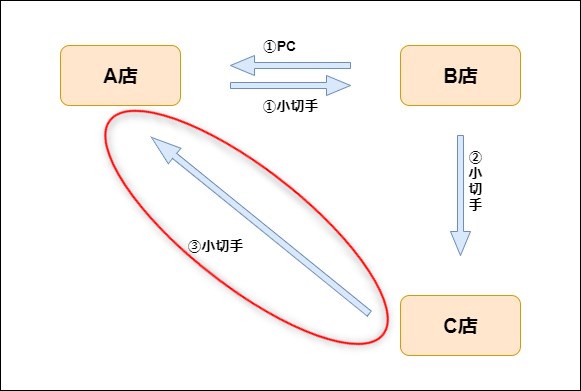
イメージ図を見ると①(A)→②(B)→③(C)と小切手が移動して、Aに戻ってきてるのがわかりますね。
なぜ、勘定科目が「現金」じゃなく「当座預金」なの?
簡単に言うと、減少するとみなしたことが減少しなかったということ。
A店は小切手を振り出したとき(①)に、貸方に『当座預金』を記帳。小切手を振り出したので、当座預金が減少したものとみなしました。ところが(③)で振り出した小切手を受け取ったわけですから、借方に『当座預金』となります。
もう一度復習しておきます。
覚えよう!
『他人振り出しの小切手を受け取ったら現金』
『自己振出の小切手を受け取ったら当座預金』
※その小切手は誰が振り出したものなのかを注意する
それでは、最後は今回のまとめで終わりたいと思います。
まとめ:【簿記初級】現金・預金を理解しよう!『個別テーマ編』


今回ご紹介した『【簿記初級】現金・預金を理解しよう!個別テーマ編』はいかがだったでしょうか?
現金
硬貨・紙幣だけじゃなく、すぐにお金に換金できるのも言う
簿記でいう現金とは、硬貨・紙幣・通貨代用証券など
論点は『通貨代用証券・現金過不足・小口現金』(初級は通貨代用証券のみ)
配当金領収証・郵便為替証書など(通貨代用証券)は、勘定科目は「現金」
預金
預金には「普通預金・定期預金・当座預金」がある
論点は「仕訳のタイミングと勘定科目・自己振出の小切手が戻ってきた場合」
他人振り出しの小切手を受け取ったら「現金」
自己振り出しの小切手を受け取ったら「当座預金」
ではまた、Hassyでした。
次回は、商品売買や手形・電子記録債権あたりを理解していきます。




を理解しよう!#6-640x360.jpg)




